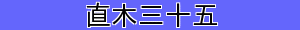直木三十五の情報(なおきさんじゅうご) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

直木 三十五さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
直木三十五と関係のある人
宮下奈都: 2016年、『羊と鋼の森』で第154回直木三十五賞候補、第13回本屋大賞受賞。 畠中恵: 2007年(平成19年) - 『まんまこと』で第137回直木三十五賞候補。 池波正太郎: 1960年(昭和35年)『錯乱』で第43回直木三十五賞 近藤隆: 文豪とアルケミスト(直木三十五) 深緑野分: 2019年、『ベルリンは晴れているか』で第160回直木三十五賞候補、第21回大藪春彦賞候補、2019年本屋大賞第3位、第9回Twitter文学賞国内編第1位に輝く。 藤原伊織: 翌年、同作で直木三十五賞も受賞した。 宇野浩二: 直木三十五(作中では仲木直吉)のなじみの待合で八重と出会ったこと、仕事場にしていた菊富士ホテル(作中では高台ホテル)に八重がしばしば訪れやがてその部屋に道具類を買い集め始めたこと、震災後に名古屋で八重と待ち合わせ京都・大阪・奈良を旅行したこと、浩二が原因で八重が旦那(作中では月給さん)と揉め事をおこし千萬のお上に仲裁してもらったこと、1924年(大正13年)から1926年(大正15年)にかけて八重と各地を旅行したこと、千萬のお上が千萬老人と別れ森井門造と同棲するようになったこと、浩二が八重とのことを妻キヌ(作中では良子)に告白してしまうこと、妻への遠慮から八重に距離を置くようになったこと、母と箱根・熱海を旅行し帰途母と別れて鵠沼の芥川龍之介(作中では有川)を訪ねたこと、浩二の神経衰弱が悪化した頃芥川が自殺したこと、八重の芸者屋の経営が悪化してきたため余儀なく新しい旦那をもったこと、浩二が八重との別れを決意したこと、2年後に直木三十五の家で八重に再会し交際が復活したこと、八重が千萬の名義を受け継いで待合を始めたこと、戦中の混乱で徐々に八重との行き来が途絶えるようになったことなどが書かれている。 井上ひさし: また多くの文学賞等の選考委員を務めており直木三十五賞、読売文学賞、谷崎潤一郎賞、大佛次郎賞、川端康成文学賞、吉川英治文学賞、岸田國士戯曲賞、講談社エッセイ賞、日本ファンタジーノベル大賞、小説すばる新人賞が挙げられる。 桜庭一樹: 第137回直木三十五賞候補になる。 北方謙三: 2000年から2023年まで、直木三十五賞の選考委員を務める。 宇野浩二: 同級生に高田保・三上於菟吉・沢田正二郎・増田篤夫、1年上級に今井白楊・広津和郎・谷崎精二、1年下級に保高徳蔵・直木三十五・田中純・青野季吉がいた。 五木寛之: 直木三十五賞 1978 - 2010年 京極夏彦: 2002年 - 『覘き小平次』で第16回山本周五郎賞受賞、第128回直木三十五賞候補。 宇野浩二: この時の宿みづうみ館はかつての片恋の相手鯉子(原とみがモデル)との思い出があり、大正10年に友人の仲木直吉(直木三十五がモデル)と、さらにその前年には有川(芥川龍之介がモデル)と滞在した宿でもあった。 葉室麟: 2010年 - 『花や散るらん』で第142回直木三十五賞候補。 海音寺潮五郎: 「天正女合戦」(『オール讀物』1936年4月号 - 7月号)と「武道伝来記」その他 (『日の出』1936年3月号)で第3回直木三十五賞(1936年上半期)を受賞。 池井戸潤: 『シャイロックの子供たち』以降は、書くものの幅を広げるため、銀行員以外の世界に踏み出そうと考え、「人間を描くんだ」と強く意識して書いた『空飛ぶタイヤ』で初めて直木三十五賞の候補となるも、「文学性に乏しい」という理由で落選となった。 寺内大吉: この頃に記者として取材に訪れた司馬遼太郎と知り合い、1957年には彼らと同人誌「近代説話」を創刊、1961年には同誌に掲載した「はぐれ念仏」で第44回直木三十五賞受賞。 宮尾登美子: 1979年 『一絃の琴』で第80回直木三十五賞 なかにし礼: 『長崎ぶらぶら節』(文藝春秋、1999年、のち新潮文庫、第122回直木三十五賞受賞) 万城目学: 続く第2作『鹿男あをによし』は第137回直木三十五賞候補となる。 山本一力: 2002年には『あかね空』で第126回直木三十五賞を受賞。 山口洋子: 1985年(昭和60年)に直木三十五賞を受賞。 東山彰良: 2015年 - 『流』で第153回直木三十五賞受賞。 村山由佳: 2003年(平成15年) 『星々の舟』で第129回直木三十五賞受賞 横光利一: 1924年、直木三十五のすすめもあり、横光の小説に共感していた映画監督の衣笠貞之助によって『日輪』は映画化された。 山本兼一: 2005年 - 『火天の城』で第132回直木三十五賞候補 横山秀夫: 2000年 - 『動機』で第53回日本推理作家協会賞(短編部門)受賞、第124回直木三十五賞候補。 戸板康二: 第42回 直木三十五賞(1960年)「團十郎切腹事件」その他(候補作の短編「團十郎切腹事件」と参考作品(対象期間外の刊行)の短編集『車引殺人事件』) 黒川博行: 1996年 - 『カウント・プラン』で第116回直木三十五賞候補 |
直木三十五の情報まとめ

直木 三十五(なおき さんじゅうご)さんの誕生日は1891年2月12日です。大阪出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 18:29更新
|
naoki sanjuugo
直木三十五と同じ誕生日2月12日生まれ、同じ大阪出身の人
TOPニュース
直木三十五と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター