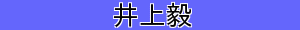井上毅の情報(いのうえこわし) 官僚 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

井上 毅さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
井上毅と関係のある人
山田顕義: 伊藤の欧米視察後、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らは憲法起草に参画し、明治22年(1889年)2月11日に大日本帝国憲法(明治憲法)公布に至ったが、日本の憲法制定に大きく携わったルドルフ・フォン・グナイスト、ローレンツ・フォン・シュタインの言及に「その頭脳の中には黄色人には憲法は不適当なり、寧ろ生意気なる所業なりとの観念を有したるが如し」との言葉がある、明治15年(1882年)に当人について学んだ伊東の意見である。 金子堅太郎: 1885年以降、内閣総理大臣秘書官として、伊藤博文のもとで井上毅、伊東巳代治らとともに大日本帝国憲法・皇室典範、諸法典の起草にあたる。 清水綋治: 明治の群像 海に火輪を 第2話「大隈重信〜明治14年の政変〜」(1976年、NHK総合) - 井上毅 伊藤博文: 同年6月から夏島で伊東巳代治・井上毅・金子堅太郎らとともに憲法草案の検討を開始する。 伊藤博文: 井上毅や伊東巳代治、金子堅太郎らとともに憲法や皇室典範、貴族院令、衆議院議員選挙法の草案の起草にあたり、1888年に枢密院が創設されるとその議長に就任し、憲法草案の審議にあたった。 ヘルマン=ロエスレル: 憲法の草案を作成したのは井上毅であったが、多くロエスレルの討議、指導によるものだったとされる。 大隈重信: 大隈は裁判所構成法の附則から違憲ではないと主張するが、井上毅法制局長官からも同様の指摘が行われた。 井上馨: 明治20年(1887年)に改正案が広まると、裁判に外国人判事を任用するなどの内容に反対運動が巻き起こり、井上毅・谷干城などの閣僚も反対に回り分裂の危機を招いたため、7月に改正交渉延期を発表、9月に外務大臣を辞任。 箕作麟祥: ちなみに、Constitution(国家の根本の法)を「憲法」と訳したのも箕作麟祥である(福澤諭吉は「律例」、加藤弘之は「国憲」、井上毅は「建国法」とそれぞれ訳していたが、箕作の訳した「憲法」という言葉が後に定着することになる)。 明治天皇: 同年に来日したドイツ人法学者ルドルフ・フォン・グナイスト(伊藤博文は憲法調査のための訪独で彼の講義を受けた)の弟子であるアルベルト・モッセ、レースレルなどお雇い外国人の法学者たちの助言を得て、憲法草案は何度も加筆修正されながら、伊藤の別荘がある神奈川県夏島に伊藤以下、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎ら伊藤側近の官僚らが集まって集中討議を行い、所謂「夏島憲法草案」がまとめられた。 矢野龍渓: しかし、井上毅から明治十四年の政変で政界を追われると、在野に下り、東京専門学校設立に携わり創立委員に就任する。 金子堅太郎: 5月、伊藤博文のもとで井上毅・伊東巳代治らとともに大日本帝国憲法・皇室典範・諸法典草案の作成に参与。 岩倉具視: しかし1880年(明治13年)頃から自由民権運動が高まり、憲法制定論議が加速し、さらに1881年(明治14年)6月下旬には法務官僚・井上毅から具申を受けたことで、岩倉もいよいよ考えを変えて、憲法制定の必要性を痛感するようになった。 横井小楠: 坂本龍馬、井上毅、由利公正、元田永孚など、明治維新の立役者や後の明治新政府の中枢の多くが後にここを訪問している。 明治天皇: しかしこの譲歩案は日本国内で朝野問わず激しい反発を巻き起こし、政府内では農商務大臣谷干城、フランス人内閣雇法律顧問ボアソナード、法務官僚井上毅などが反対の論陣を張った。 池辺義象: 大日本帝国憲法制定に携わった井上毅の国典研究の助手を務めた。 末広鉄腸: 1875年(明治8年)10月、朝野新聞の編集長となり、成島柳北社長の洒脱な諷刺『雑録』と鉄腸の痛烈な『論説』とで人気を集めたが、1876年(明治9年)2月に、讒謗律・新聞紙条例の制定者、井上毅・尾崎三良を紙上で茶化し、柳北は禁獄4ヶ月と100円、鉄腸は8ヶ月と150円の罰を受け、収監された。 ヘルマン=ロエスレル: 彼の思想は保守的で国家の権限強化する方向にある一方で、法治国家と立憲主義の原則を重んじるものであった(これは、彼から深い薫陶を受けた井上毅の思想にも影響する)。 明治天皇: この草案を読んだ法務官僚井上毅は、こんな宗教家の説教のようなことを論じても国民は聖勅と信じないだろうとして同案に反対した。井上毅は開明派官僚として西洋学に通じ、伊藤博文のもとで憲法草案の起草にあたった人物であるが、熊本藩士時代には木下犀潭の門人として漢学にも通じていた。 片岡直輝: 同年9月、河野内相が文部大臣になると再び文相秘書官となるが、1893年(明治26年)3月、文相が井上毅へ親任されるに際して依願免官となると、内務省に復帰し大阪書記官に任命される。 明治天皇: 第1回議会が平穏に終わることができたのは聖旨を呈して、忍び難きを忍んで民党に多大な譲歩を行った山縣の功績といわれ、3月4日には井上毅も山縣に称賛と労いの書簡を送っている。 西園寺公望: 明治27年(1894年)には病気で辞任した井上毅の後任の文部大臣として、第2次伊藤内閣に初入閣を果たした。 明治天皇: しかし法務官僚の井上毅が「謹具意見」と題した反論を提出して女帝論に反対した。柳原前光もこの頃から審議に加わるようになり(彼の妹の愛子が明治天皇に入内して明宮嘉仁親王(大正天皇)を儲けており、宮中に影響力があった)、また井上毅はレースレルにも知恵を借りて起草作業を勧めた。 横井小楠: そのほか、学問と政治のむすびつきを論じた嘉永5年(1852年)執筆の『学校問答書』、マシュー・ペリーやエフィム・プチャーチンへの対応についての意見書である嘉永6年(1853年)執筆の『夷虜応接大意』、元治元年(1864年)の井上毅との対話の記録『沼山対話』、慶応元年(1865年)の元田永孚との対話の記録『沼山閑話』などがある。 西沢利明: 春の波涛(1985年) - 井上毅 ローレンツ=フォン=シュタイン: これには伊藤とともに憲法草案を執筆した井上毅がシュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景にはシュタインの存在が大きい。 伊東巳代治: 明治19年(1886年)から井上毅・金子堅太郎と共に大日本帝国憲法起草に参画。 明治天皇: 21日に元田が危篤状態となったとの報告を受けた天皇は、侍講、修学顧問として二十余年にもわたって天皇に仕えてきた元田に感謝し、彼を華族の男爵位に列するとともに、従二位の官位を与えることにし、井上毅を勅使として元田邸に派遣して元田に勅語を伝えた。 清水紘治: 明治の群像 海に火輪を 第2話「大隈重信〜明治14年の政変〜」(1976年、NHK総合) - 井上毅 明治天皇: しかし法務官僚の井上毅は、内閣総理大臣の権限が巨大すぎると、天皇親政の原則を侵しかねないとして大宰相主義に反対した。 |
井上毅の情報まとめ

井上 毅(いのうえ こわし)さんの誕生日は1844年2月6日です。熊本出身の官僚のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 09:29更新
|
inoue kowashi
井上毅と同じ誕生日2月6日生まれ、同じ熊本出身の人
TOPニュース
井上毅と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター