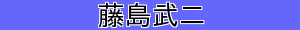藤島武二の情報(ふじしまたけじ) 洋画家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

藤島 武二さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
藤島武二と関係のある人
山口薫: 4年次に旧制水戸高校理科を受験するも失敗し、5年の冬に上京し当時藤島武二が洋画を指導していた川端画学校で学ぶ。 和田英作: 東京美術学校(現・東京芸術大学)に西洋画科が開設されると、黒田の西洋画科教授就任にともなって、藤島武二・岡田三郎助とともに助教授に就任。 フェルナン=コルモン: このアトリエやエコール・デ・ボザールでコルモンの指導を受けた画家には、フィンセント・ファン・ゴッホ、トゥールーズ=ロートレック、エミール・ベルナール、ルイ・アンクタン、ジョン・ピーター・ラッセル、アルベール・マルケ、藤島武二、山下新太郎、シャイム・スーティンなどがいる。 佐分真: 翌年、東京美術学校西洋画科に入学し、藤島武二に学ぶ。 小堀杏奴: 1931年(昭和6年)、類とともに画家藤島武二に師事。同年11月、藤島武二の仲人で画家小堀四郎と結婚。 杉浦幸雄: 中学卒業時の1929年、東京美術学校を受験するが、デッサンの実技試験中にタバコを吸ったことを試験監督の藤島武二にとがめられて口論となり、試験会場を追い出され、不合格に終わった。 嘉門安雄: 『青木繁 / 藤島武二』(河北倫明共編、集英社、現代日本美術全集7) 1972 岡本一平: 東京・大手町の商工中学校から東京美術学校西洋画科に進学し、藤島武二に師事する。 アルフォンス=ミュシャ: ミュシャの挿絵やイラストが、明治時代の文学雑誌『明星』において、挿絵を担当した藤島武二により盛んに模倣された。 折田彦市: 1912年(明治45年)5月1日の創立記念日に、三高で肖像画(藤島武二画)の除幕式が行われた。 若松光一郎: 藤島武二教室に入る(同級生に杉全直・鎌田正蔵・土橋淳・鈴木新夫・1年後輩に佐藤忠良) 里見浩太朗: およう(2002年) - 藤島武二 荻須高徳: 小石川(現・文京区)にあった川端画学校に入り、藤島武二に師事する。 曾宮一念: 大下藤次郎、藤島武二、黒田清輝に指導を受ける。 曾宮一念: 藤島武二、黒田清輝、山下新太郎らに指導を受ける。 香月泰男: 山口県立大津中学校(現・山口県立大津緑洋高等学校)卒業後、川端美術学校を経て1931年に東京美術学校に入学、藤島武二の教室に学ぶ。 猪熊弦一郎: 1922年 - 東京美術学校(現・東京芸術大学)洋画科に入学し、藤島武二に師事する。 佐伯祐三: 1917年(大正6年)東京の小石川(現・文京区)にあった川端画学校に入り、藤島武二に師事する。旧制北野中学(現・大阪府立北野高等学校)を卒業した後、1918年(大正7年)には東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学し、引き続き藤島武二に師事、1923年(大正12年)に同校を卒業した。 清水対岳坊: 東京美術学校予科や川端画学校で藤島武二に洋画を学ぶ。 折田彦市: 1912年(明治45年)5月1日(三高創立記念日)に、藤島武二が描いた折田の肖像画の除幕式が行われた。 有島生馬: 岩元禎に紹介を頼み、大学の卒業式が終了したその足で洋画家藤島武二のもとを訪ね、住み込みの生徒となるが、しばらくして駒込円通寺に転居し、日露戦争終戦後の時期である1906年(明治39年)5月、イタリアに向かう。 長谷川潔: 1910年(明治43年)に麻布中学校を卒業した後、葵橋洋画研究所で黒田清輝から素描を、本郷洋画研究所で岡田三郎助、藤島武二から油彩を学ぶ。 西脇順三郎: 白滝幾之助や藤島武二らに相談した末、黒田清輝主宰の「白馬会」に入会するが、画学生の気風になじめず、父の急死により画家の道を断つ。 長原孝太郎: 明治28年7月には黒田清輝の下で洋画を学び、翌明治29年(1896年)には清輝、久米桂一郎、藤島武二らと共に白馬会の結成に参加、同年開催された第一回白馬会展に「森川町遠望」(水彩)、「牛屋(牛肉屋の二階)」(狂画)、「焼芋屋」(狂画)、「車夫」(狂画)の4点を出品、以降も作品の出品を重ねた。 前田寛治: 学校では長原孝太郎と藤島武二に師事する。 森類: 1931年には次姉の小堀杏奴と共に藤島武二に師事。 清水良雄: 黒田清輝、藤島武二に師事する。 小山敬三: 1916年(大正5年) 父の反対を押し切り、画家になるために慶應義塾大学理財学科を中退し、川端画学校で藤島武二に師事。 伊原宇三郎: 1916年(大正5年)東京美術学校西洋科に入学、藤島武二に学ぶ。 今東光: 1915年、上京して小石川茗荷谷の伯父の家に寄食し、「太平洋画会/太平洋美術会」(中村不折)、「川端画塾/川端画学校」(主任教官 藤島武二)に通い、画家を目指しながら文学も志し東郷青児、関根正二らと親交を結び、生田長江に佐藤春夫を紹介される。 |
藤島武二の情報まとめ

藤島 武二(ふじしま たけじ)さんの誕生日は1867年10月15日です。鹿児島出身の洋画家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/03 19:00更新
|
fujishima takeji
TOPニュース
藤島武二と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター