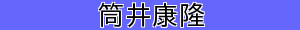筒井康隆の情報(つついやすたか) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

筒井 康隆さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
筒井康隆と関係のある人
タモリ: 持ちネタの一つであった昭和天皇の物真似については、1985年5月14日、作家の筒井康隆のパーティーで披露したところ、それが翌週の「週刊読書人」に掲載され、右翼から脅迫を受けることとなり、最終的には所属事務所の田邊昭知社長が半監禁状態で右翼から抗議される事態に至った。 山下洋輔: 1986年3月21日 『スタア』 筒井康隆大一座=プルミエ・インターナショナル【都留(作曲家)】 斎藤十一: また筒井康隆も若手時代に苦汁を飲まされた一人であるという。 山上たつひこ: アフリカの爆弾(原作:筒井康隆)(『週刊漫画TIMES』1974年1月19日号~3月2日号) 宮崎敦吉: 人間狩り (筒井康隆作) 伊藤典夫: また、筒井康隆編集の雑誌「面白半分」に、「世界文学名作メチャクチャ翻訳」を連載した。また、筒井康隆のドタバタSF『色眼鏡の狂詩曲』(1968)では、ほぼ本人そのままの設定で(名前は江藤典磨)主要登場人物となっている。 君塚良一: ボクたちのドラマシリーズ『時をかける少女』(フジテレビ、1993年2月 - 3月) - 原作:筒井康隆 大藪春彦: 筒井康隆の短編「優越感」(「三丁目が戦争です」を戸建て住民側視点で描いたもの。 横田順彌: 雑誌には筒井康隆、平井和正や浅倉久志も寄稿した。 かんべむさし: 同じ関西在住の先輩作家の小松左京や筒井康隆から目をかけられ、小松から米朝一門に、筒井から山下洋輔トリオに紹介され、それぞれ交流が始まった。 江戸川乱歩: 晩年には、SF小説に興味を持ち、筒井康隆、矢野徹など、黎明期の日本のSF関係者を援助し、商業出版に尽力した。 平岡正明: 筒井康隆断筆をめぐるケンカ論集(ビレッジセンター出版局 1994年9月) 栃赤城雅男: 筒井康隆の著作を愛読していた。 さとう珠緒: 筒井康隆劇場「エロティックな総理」(2006年、GyaO) 長谷邦夫: またこの年に朝日ソノラマのサンコミックスから筒井康隆原作をもとに長谷邦夫がコミカライズした『東海道戦争』が出版される。 正本ノン: 筒井康隆と大島弓子の大ファンであるという。 松田洋治: 筒井康隆笑劇場(2024年3月8日 - 14日、シアター・アルファ東京) 山田正紀: かんべむさし、堀晃らとともに、星新一、小松左京、筒井康隆らの日本SF第一世代に続く、第二世代と呼ばれる。 磯秀明: スイートホームズ探偵(作:筒井康隆 演出:川和孝) 薄井ゆうじ: 筒井康隆、小林恭二、堀晃、佐藤亜紀との5名で、「JALInet」(JAPAN LITERATURE net)を、発起人として創設したことがある。 河野典生: ともにジャズファン、山下ファンということで、筒井康隆とも親交があった。 石山透: 1971年、筒井康隆の『時をかける少女』を大幅に膨らませた、少年ドラマシリーズ第一作『タイム・トラベラー』が好評で、オリジナル続編を執筆し、自身で『続・時をかける少女』として小説化。 藤岡真: 1992年『笑歩(しょうほ)』で第10回小説新潮新人賞受賞(選考委員;井上ひさし、筒井康隆)。 塩見鮮一郎: かつて『黄色い国の脱出口』で差別者扱いされたにもかかわらず、いわゆる差別表現に関しては積極的に自主規制を推進する立場を取り、筒井康隆と日本てんかん協会の和解(1994年)に際しては、本田雅和と共に『朝日新聞』紙上で筒井を激しく糾弾した。 南山宏: また、1971年には筒井康隆『脱走と追跡のサンバ』でシリーズ「日本SFノヴェルズ」を刊行開始している。 山下洋輔: 山下が初代会長を務めた「全日本冷し中華愛好会(全冷中)」による「第1回冷し中華祭り」(1977年4月1日)や、「筒井康隆断筆祭」(1994年4月1日)でも演奏されている。 加藤昌史: 『時をかける少女』(2015年) - 筒井康隆原作 山本直樹: 高校時代は、筒井康隆の小説を読んで本の面白さに目覚める一方、下宿先の女性の先輩から『りぼん』を借りて読んでいた。 長尾みのる: ジャングルめがね 筒井康隆 著,長尾みのる 画 小学館 1977 (小学館の創作童話シリーズ ; 39) 舛田利雄: また『大都会』などの石原プロ作品をはじめとしたテレビ映画の演出も数多く手掛けるほか、筒井康隆作品の初映画化である『俺の血は他人の血』以後、日本SF大賞を受賞した小松左京原作の映画化作『首都消失』など、SFや特撮映画の演出も多い。 |
筒井康隆の情報まとめ

筒井 康隆(つつい やすたか)さんの誕生日は1934年9月24日です。大阪出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 15:38更新
|
tsutsui yasutaka
筒井康隆と同じ誕生日9月24日生まれ、同じ大阪出身の人
TOPニュース
筒井康隆と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター