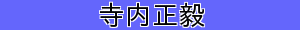寺内正毅の情報(てらうちまさたけ) 軍人 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

寺内 正毅さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
寺内正毅と関係のある人
上原勇作: 1908年(明治41年)12月 - 第7師団長(陸軍大臣:寺内正毅) 倉成正: 寺内正毅 小村寿太郎: 内閣からは桂、小村、山本権兵衛海相、寺内正毅陸相、元老からは伊藤、山縣、井上、松方、大山巌が参加した。 山県有朋: 大隈首相は自らの後継を加藤高明と考えており、山縣は次の内閣を寺内正毅にしようと考えていた。 渡辺淳一: 1970年に37歳で総理大臣寺内正毅をモデルとしたとされる『光と影』で第63回直木賞を受賞し、本格的に作家活動を開始した。 宇多田照實: 第18代内閣総理大臣寺内正毅は照實の伯叔祖父。 徳富蘇峰: 1910年(明治43年)、韓国併合ののち、初代朝鮮総督の寺内正毅の依頼に応じ、朝鮮総督府の機関新聞社である京城日報社の監督に就いた。 宇多田ヒカル: 先祖には、第18代内閣総理大臣・寺内正毅が居り、ヒカルは、寺内の曾姪孫にあたる。 大隈重信: 6月24日、大隈は大正天皇に辞意を示し、後継に加藤と寺内正毅大将を推薦し、隈板内閣のような両者共同の内閣を作ろうとした。 原敬: 元老筆頭で上原の庇護者でもある山縣有朋は、自派の寺内正毅と政友会を連携させた内閣を目論んでおり、この時点で政友会と対立することは望んでいなかった。 三川雄三: 第10話「小村寿太郎」 - 寺内正毅 明治天皇: 軍議の臨席者は、参謀総長有栖川宮熾仁親王(薨去後には小松宮彰仁親王)、参謀次長・兵站総監川上操六、野戦監督長官野田豁通、運輸通信長官寺内正毅、野戦衛生長官石黒忠悳、陸軍大臣大山巌、海軍大臣西郷従道、海軍軍令部長樺山資紀、侍従武官長・軍事内局長岡沢精(ただし彼は議席には列さず、軍議中常に天皇の御側に侍立していた)、その他陸海軍参謀2名、管理部長1人(この3人は御用の時のみ呼び出される)といった軍人たちの他、文官から内閣総理大臣伊藤博文、外務大臣陸奥宗光等も臨席した。 長谷川好道: この間、伯爵に陞爵した長谷川は1916年(大正5年)10月16日、寺内正毅の後任として朝鮮総督に就任する。 山県有朋: 山縣直系の桂・児玉や寺内正毅が陸相を歴任していった。 石本新六: 陸軍総務長官を経て、日露戦争時は陸軍次官(法務局長兼任)として寺内正毅陸軍大臣を支えた。 中橋徳五郎: このように中橋は、寺内正毅内閣以来の課題であった、高等教育機関大増設の中心人物であったが、大正10年度の予算編成では、東京および広島高等工業学校、神戸高等商業学校の大学昇格計画が承認されず、中橋文相食言事件として政治問題化した。 上原勇作: 5月 参謀本部第2局員(第2局長:寺内正毅) 上原勇作: 9月29日 - 工兵中尉(フランス公使館附武官:寺内正毅) 三浦謹之助: 明治天皇、大正天皇、貞明皇后、昭和天皇、山縣有朋、西園寺公望、松方正義、大隈重信、桂太郎、寺内正毅、原敬、加藤高明、浜口雄幸、犬養毅、井上馨、平沼騏一郎、牧野伸顕、福沢諭吉、中村福助、三浦環、小唄勝太郎、大倉喜八郎、安田善次郎、福沢桃介 河合良成: 大正7年(1918年)8月外米課長のとき、郷里の富山県で米騒動が起き全国に波及し、寺内正毅内閣が総辞職したのを受けて引責辞任した。 上原勇作: 1877年(明治10年)5月 - 陸軍士官学校(旧3期)入学(学生中隊長:寺内正毅) 木村俊夫: 寺内正毅 平田東助: 陸軍および内務系官僚に広範な「山縣閥」を築いた山縣側近の中で、陸軍の側近が桂太郎・児玉源太郎・寺内正毅らとすれば、平田は清浦奎吾・田健治郎・大浦兼武らと並ぶ官僚系の山縣側近として人脈を形成した。 大正天皇: 大隈は翌1916年(大正5年)6月に内閣総辞職の意を奏上し、後継に加藤高明と寺内正毅を推薦し、かつての隈板内閣のような内閣を作ろうとした。 山県有朋: 大本営で策定される満州軍総司令部への命令は、事前に山縣と寺内正毅陸軍大臣に内示され、山縣は戦争指導の中枢を務めることとなった。 明石元二郎: 明治43年(1910年)7月、寺内正毅朝鮮統監の下で憲兵司令官と警務総長を兼務し、朝鮮併合の過程で武断政治を推し進めた。 大村益次郎: 10月1日、益次郎は河東操練所生徒寺内正毅(のち陸軍大将、総理大臣)、児玉源太郎(のち陸軍大将)らによって担架で運ばれ、高瀬川の船着き場から伏見で1泊の後、10月2日に大阪八軒家に到着、そのまま鈴木町の大阪府医学校病院に入院する。 原敬: 1916年(大正5年)10月9日、山縣の奏薦で寺内正毅が首相となり、寺内内閣が成立した。 西園寺公望: 西園寺は大正5年(1916年)3月に大正天皇に拝謁し、加藤はまだ適当ではなく、原か寺内正毅が適当であると奏上している。この会議では寺内正毅が首相に奏薦された。 大正天皇: 皇太子も大陸への出征に積極的であったが、皇太子が出征することはかつての日本で始めてのことであり、なれない現場の指揮が混乱するとの桂太郎首相や寺内正毅陸軍大臣の反対を受けて実現せずに終わった。 |
寺内正毅の情報まとめ

寺内 正毅(てらうち まさたけ)さんの誕生日は1852年3月25日です。山口出身の軍人のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 13:23更新
|
terauchi masatake
寺内正毅と同じ誕生日3月25日生まれ、同じ山口出身の人
TOPニュース
寺内正毅と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター