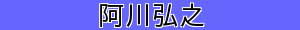阿川弘之の情報(あがわひろゆき) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

阿川 弘之さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
阿川弘之と関係のある人
須賀敦子: 選考委員は瀬戸内寂聴・田辺聖子・阿川弘之・大庭みな子・佐伯彰一。 池島信平: 源氏鶏太、阿川弘之、豊田穣などが会員だった。 グレアム=グリーン: 小さなきかんしゃ(1946年)(阿川弘之訳 エドワード・アーディゾーニ絵 文化出版局、1975年) 岡部冬彦: 『へりこぷたーのぶんきち』(阿川弘之作) 大久保房男: 自らと同じく国文学学生から海軍に入った阿川弘之とは編集者時代から長年にわたって親交があり、たびたび随筆などでその言動が「鬼のおくび」というニックネームのもとで記されている。 福田恆存: 葬儀委員長は作家阿川弘之で、林健太郎、久米明等が弔辞を述べた。 阿川佐和子: 作家・阿川弘之の長女として東京都に誕生。 谷川徹三: その流れで、作家阿川弘之とは志賀直哉ら白樺派関係で、平岩外四とは同郷でもあり終生交流があった。 吉行淳之介: 同人雑誌を通して安岡章太郎、近藤啓太郎、阿川弘之、三浦朱門、島尾敏雄らと知り合った。 米内光政: また実松の自伝によるとこれは山本の発案で、米内は「やりすぎではないか」と「消極的だった」と記しており、阿川弘之が書いた、米内・山本の「共謀」とは少し展開が違っている。 西田健: 読書が趣味で志賀直哉、阿川弘之、曽野綾子、佐藤愛子、福田恆存、丸谷才一、高坂正堯、佐伯啓思、塩野七生の愛読者であり、海外ミステリー(特に英国)にも広く通じている。 武田鉄矢: 父は1983年に死去し、生前武田は父とは和解できなかったが、父の死後に戦争経験者である司馬遼太郎や阿川弘之の作品を読んだり、シベリア抑留経験者の吉田正や三波春夫の曲を聴いたりするうちに、武田は父の不機嫌の正体、言葉で表せないトラウマを理解するようになった。 安岡章太郎: その当時コルセットをつけながら、吉行淳之介や阿川弘之と盛り場などを遊び歩いたと言う。 阿川尚之: 父は小説家の阿川弘之。 直井潔: その伝は阿川弘之『志賀直哉』(新潮文庫、上下)にくわしい。 島尾敏雄: 同人には島尾敏雄のほか矢山哲治、真鍋呉夫、阿川弘之、那珂太郎、小島直記、一丸章らがおり、同人は長崎高商と福岡高校の2つの系統からなっていた。 古山高麗雄: 阿川弘之は、「兵隊生活を観念的でなく、一兵卒として描ける素晴らしい作家でした」と追悼している。 安川定男: 阿川弘之とは東大および海軍で同期である。 金田浩一呂: 文芸記者として、井伏鱒二、遠藤周作、城山三郎、阿川弘之らと交友。 藤島泰輔: ペンクラブからは有吉佐和子・司馬遼太郎・立原正秋などが脱会、理事だった安岡章太郎や阿川弘之が辞意を表明するなど、運営に大きな混乱を起こした。 丹羽文雄: 東京の小金井カントリー倶楽部や夏の間は別荘のあった軽井沢の軽井沢ゴルフ倶楽部などで源氏鶏太、柴田錬三郎、阿川弘之といった文士たちが丹羽と共にゴルフを楽しむ為に集ったことも多かったことから、いつしか『丹羽学校』という呼び名も付けられた程である。 綱淵謙錠: 同年12月、当時ペンクラブ専務理事の阿川弘之から「事務局長になって欲しい」との要請に負け翌年1月から出勤、さらに事務所を訪れた前会長の川端康成に「今年は何も書かずにクラブの仕事だけにして欲しい。 近藤啓太郎: 第三の新人の一人に数えられ、阿川弘之、吉行淳之介、安岡章太郎らとは終生親しくつきあった。 石井桃子: この文庫の一番乗りはロックフェラー財団つながりで交友があった阿川弘之の長男尚之だった。 梶山季之: 1957年に広島県出身者の阿川弘之、藤原弘達、木村功、桂芳久、杉村春子で「7の会」を結成(または毎年故郷の銘酒「賀茂鶴」を呑む「カモツル会」)。 ポール=セロー: ふしぎなクリスマス・カード (阿川弘之 訳、ジョン・ロレンス 絵 講談社 1979年) 谷川徹三: 弔辞は阿川弘之が読んだ。 岩瀬順三: 阿川弘之の本 (1970年) 八島太郎: 阿川弘之は『からすたろう』の日本語版に寄せた文章で「八島さんにとって『日本』とは東京でも富士山でも奈良でも京都でもなく、彼が生まれ育った鹿児島県の僻村だという。 ポール=セロー: 鉄道大バザール (阿川弘之 訳 講談社 1977年 のち講談社文庫、講談社文芸文庫) |
阿川弘之の情報まとめ

阿川 弘之(あがわ ひろゆき)さんの誕生日は1920年12月24日です。広島出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 19:49更新
|
agawa hiroyuki
TOPニュース
阿川弘之と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター