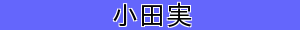小田実の情報(おだまこと) 作家、平和運動家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

小田 実さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
小田実と関係のある人
吉川勇一: 同年小田実代表のベトナムに平和を!市民連合(ベ平連)の2代目事務局長になり、1974年のベ平連解散まで務める。 柴田翔: 『季刊 人間として』(小田実, 開高健, 高橋和巳, 真継伸彦共同編集、筑摩書房) 1970 - 1971 開高健: 帰国(1965年2月24日)後は小田実らのベ平連に加入して反戦運動をおこなったが、ベ平連内の反米左派勢力に強く反発し脱退、過激化する左派とは距離を置くようになる。 五木寛之: 『五木寛之討論集 箱舟の去ったあと』(羽仁五郎、小田実、久野収他) 講談社、1973年 真継伸彦: 『変革の思想を問う』小田実・高橋和巳・真継伸彦共編 筑摩書房 1969年 有田芳生: この編集を手掛けたことで、小田実との対談記事掲載以来の査問が有田へ始まり、党規律違反として除籍処分を受ける。有田は2022年に小田実対談記事掲載の時よりも日本共産党の対応は硬直的だったとし、「赤旗」から3回連載で『日本共産党への手紙』を批判されたこと、賛同していたはずの上田副委員長が「だから(出版を)やめろと言っただろう!」と掌返ししたことで言葉を失ったとし、「これが、『政治的人間』というものか」と思ったと明かしている。 柴田翔: 1970年から1972年まで小田実、高橋和巳、真継伸彦、開高健とともに同人誌『人間として』を筑摩書房から刊行。 黒古一夫: 2019年6月からは、批評家生活40年を記念して『黒古一夫 近現代作家論集』(全6巻、第1巻北村透谷論・小熊秀雄論、第2巻大江健三郎論・林京子論、第3巻村上春樹論、第4巻村上龍・立松和平論、第5巻小田実論・野間宏論・辻井喬論、第6巻三浦綾子論・灰谷健次郎論・井伏鱒二論アーツアンドクラフツ)を刊行する。 吉川勇一: ベ平連の解散後、小田実、色川大吉らを中心とした「日本はこれでいいのか市民連合」(日市連)(1980年 - 1994年)に参加するが、1987年に小田の東京都知事選挙への出馬の是非を巡って日市連内で対立が起こり会を離れる。 山口文憲: ベ平連の活動で、鶴見俊輔、小田実、武藤一羊、鶴見良行、室謙二らを知る。 小熊英二: 鶴見俊輔、小田実、吉川勇一らのベ平連について小熊は『<民主>と<愛国>』で評価しているが、大学紛争期の全共闘をはじめとする新左翼に対しては、批判的なスタンスを取っている。 富士正晴: 書画もよくし、東京の文春画廊で個展を開いた際、親交のあった鶴見俊輔がこの会場から小田実と連絡をとり、ベ平連運動が始まるきっかけとなったという逸話がある(ベトナム北爆には衝撃を受けるかたわらで、魯迅を読むことで沈鬱さの平衡を保っていた)。 鈴木明: また小田実は、「本多勝一さんが書いた“南京大虐殺”についての記事には、“百人斬り”をした将校のことがでていた。 高橋和巳: 『変革の思想を問う』小田実・真継伸彦共編 筑摩書房 1969年 長谷川海太郎: 小田実の『何でも見てやろう』が出た今日でも、なお新鮮な魅力を持っている。 早坂茂三: この各回では、元警察官僚の佐々淳行や作家の小田実と共演している。 牧野剛: 1987年に、河合塾の研究機関である河合文化教育研究所に、作家の小田実を招いたのも彼の尽力による。 中薗英助: 1974年には大江健三郎、小田実などとともに日本アジア・アフリカ作家会議設立の呼びかけ人となった。 鶴見俊輔: 2004年6月には、大江健三郎や小田実らと共に九条の会の呼びかけ人となる。 大島渚: 「朝まで生テレビ」において小田実らに対し「ばかやろう」と発言し、話題になったことが複数回ある。 小松左京: 1966年には、東京12チャンネルに勤務していたばばこういちが主宰で、「ベトナム戦争についてのティーチ・イン」を行った際、小松は小田実や開高健らとともに参加し、ベトナム戦争反対論を論じた。 山下芳生: 作家の小田実らとともに市民=議員立法による「災害被災者等支援法案」の成立のために奔走。 黒古一夫: 1982年、西ドイツから始まった世界的な「反核運動」に連動し中野孝次や小田実らが始めた「核戦争に反対する文学者の署名運動」(通称「文学者の反核運動」の事務局に関わり、東京、広島、長崎で開催された反核集会を準備する。 坂本一亀: 小田実は1950年代に河出書房から2冊の小説を出版していたが売れなかった。 高橋和巳: 『季刊 人間として』小田実 開高健 柴田翔 高橋和巳 真継伸彦 (共同編集) 筑摩書房 1970 - 1971 辻元清美: 高校3年生のとき、代々木ゼミナール名古屋校で英語の講師をしていた小田実の講演を聞く。 有田芳生: 1980年の「文化評論」に、事前に宮本顕治日本共産党委員長(当時)も了解した企画である上田日本共産党副委員長と作家の小田実の対談を掲載した。掲載号は完売した数カ月後に、小田実が公の場で共産党を「市民運動などを自党に系列化する既成政党」と批判した。この日本共産党批判を受けて、共産党と小田実の関係が悪化した余波で党内で有田までも批判された。後の2005年に小田実と上田副委員長が再び対談し、雑誌掲載されたが、日本共産党による対立の総括・和解経緯説明は一切なかった。 牛島秀彦: 英語の殺し文句 もっと英語で自分を主張しよう 華麗なる説得技法 小田実共著 ベストセラーズ 1993 (ワニの本) 澤地久枝: 『憲法九条、あしたを変える 小田実の志を受けついで』井上ひさし,梅原猛, 大江健三郎, 奥平康弘, 加藤周一,鶴見俊輔,三木睦子,玄順恵共著 岩波ブックレット 2008 小中陽太郎: 1965年、小田実たちと共にベ平連を結成。 |
小田実の情報まとめ

小田 実(おだ まこと)さんの誕生日は1932年6月2日です。大阪出身の作家、平和運動家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/30 07:55更新
|
oda makoto
小田実と同じ誕生日6月2日生まれ、同じ大阪出身の人
TOPニュース
小田実と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター