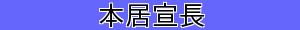本居宣長の情報(もとおりのりなが) 国学者 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

本居 宣長さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
本居宣長と関係のある人
大野晋: 『本居宣長全集』 筑摩書房(全20巻・別巻3)、1968〜93年。 芳賀登: 4 本居宣長の学問と思想 末松安晴: 父は、折に触れて農作業や魚釣りなどへ連れ出し、木曽川の対岸に咲く白い花を教材に、「敷島の大和心を人とわば 朝日に匂う山桜花かな」(本居宣長の短歌)などと教えたりした。 平田篤胤: 当初は、本居宣長らの後を引き継ぐ形で、儒教・仏教と習合した神道を批判したが、やがてその思想は宣長学派の実証主義を捨て、神道的方面を発展させたと評されることが多い。 竹内浩三: 遺品は本居宣長記念館に寄贈されている。 芳賀登: 『近世国学の大成者 本居宣長』1984(清水新書) 敷島勝盛: 四股名は師匠である14代立田川の知人で、本居宣長の和歌「敷島の大和心を人とはば朝日に匂う山桜花」から引用して、曙の名も考えた大阪のちゃんこ屋経営者が付けた。 平田篤胤: 篤胤が本居宣長の名前と著作を知ったのは、宣長没後2年経った享和3年(1803年)のことであった。 大和心: 江戸時代になると、中期以降の国学の流れの中で上代文学の研究が進み、大和魂の語は本居宣長が提唱した「漢意(からごころ)」と対比されるようになって(真心)、「もののあはれ」「はかりごとのないありのままの素直な心」「仏教や儒学から離れた日本古来から伝統的に伝わる固有の精神」のような概念が発見・付与されていき、後期には「日本の独自性を主張するための政治的な用語」として使われるようになった。 大西瀧治郎: また大西は各隊に本居宣長の歌「敷島の大和心を人問わば朝日に匂ふ山桜花」から敷島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊と命名した。 橋本進吉: これについては、水谷静夫が論じているほか、21世紀に入っての研究で、本居宣長や石塚龍麿の研究に従っていることが確認されている。 熊野純彦: 『本居宣長』(作品社) 2018年 金田一春彦: それまで中国本国でも不明になっていた唐代の四声の音価を明らかにし、それによって『類聚名義抄』から契沖や本居宣長に至る文献の四声を解釈し、平安時代から現代に至る京都語のアクセントの時代的変化を明らかにした。 藤田東湖: 会沢正志斎と並ぶ水戸学の大家として著名であるが、藤田は本居宣長の国学を大幅に取り入れて尊王の絶対化を図ったほか、各人が積極的に天下国家の大事に主体的に関与することを求め、吉田松陰らに代表される尊王攘夷派の思想的な基盤を築いた。 丸山眞男: 第二次世界大戦中に執筆した『日本政治思想史研究』は、ヘーゲルやフランツ・ボルケナウらの研究を日本近世に応用し、「自然」-「作為」のカテゴリー を用いて儒教思想(朱子学)から荻生徂徠・本居宣長らの「近代的思惟」が育ってきた過程を描いたものである。 折口信夫: 両者は国学発展の祖に当たる賀茂真淵・本居宣長と同じく、教えを受けながらも正当だと思ったところは譲らず、真理の追求を磨く学者の関係を持っていたといえる。 田中優子: 『江戸百夢』については、丸谷才一が「世界の中の江戸文化といふ関心は全巻にみなぎつてゐる」(「国際的把握」)「本居宣長とはまた違ふ角度からの日中文化比較論で、やまとごころを宣揚してゐる」「特筆に値するのは文章がいいこと」(例えば、事物の「列挙」)と評した。 日野龍夫: 『本居宣長集 新潮日本古典集成』新潮社 1983年、新装版2018年 亀井秀雄: そして、逍遥が取り上げた滝沢馬琴の物語作法論や本居宣長の源氏物語論を、実作の細部と照合しながら分析をした。 長谷川如是閑: 1936年(昭和11年)の二・二六事件に際しては『老子』を著し、また『本居宣長集』を編集している。 小林一茶: また、豊富な勉学の中で一茶は本居宣長の玉勝間、古事記伝などを読み、当時広まってきた国学思想に傾倒していく。 成田為三: 敷島の(本居宣長 詞) 平田篤胤: 復古神道(古道学)の大成者であり、大国隆正によって荷田春満、賀茂真淵、本居宣長とともに国学の四大人(しうし)の中の一人として位置付けられている。 川路聖謨: 執筆動機は、ミサンザイ、丸山、塚山の三説が鼎立するなか、本居宣長が『古事記伝』においてスイセン塚古墳を神武陵としたことへの批判だと述べている。 千家尊福: 本居宣長は、記紀をもとに「顕事(あらわごと)」と「幽事(かくりごと)」との対立軸を著し、「顕事」とは現世における世人の行う所業(=頂点は天皇が行う政(まつりごと))であり、「幽事」とは目に見えない神の為せる事(=統治するのは大国主神)であるとした。 中上健次: 中上はこの怪異物語、悪漢物語の作者を論争の相手である本居宣長と対置したうえで称揚している。 三上章: 日本語文法研究を志す決意をしたとき、本居宣長の墓に詣でたという。 芳賀登: 『本居宣長 近世国学の成立』清水書院 1972/吉川弘文館〈読みなおす日本史〉 2017 芳賀登: 『本居宣長』牧書店(世界思想家全書)1965 平田篤胤: 本居宣長は、古典に照らして、人の魂はその死後、黄泉に行くと考えたともされる。 |
本居宣長の情報まとめ

本居 宣長(もとおり のりなが)さんの誕生日は1730年6月21日です。三重出身の国学者のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/07/01 10:17更新
|
motoori norinaga
本居宣長と同じ誕生日6月21日生まれ、同じ三重出身の人
TOPニュース
本居宣長と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター