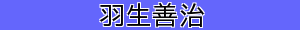羽生善治の情報(はぶよしはる) 将棋 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

羽生 善治さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
羽生善治と関係のある人
深浦康市: 2007年度、第48期王位戦で羽生善治に挑戦。 斎藤慎太郎: 第88期(2017年度)棋聖戦決勝トーナメントで森内俊之、木村一基・郷田真隆・糸谷哲郎を破り、羽生善治への挑戦権を獲得。 橋本崇載: 結果、羽生善治に敗れて2勝7敗・10位となり、1期でB級1組へ降級した。 酒井邦嘉: 共著者は、曽我大介、羽生善治、前田知洋、千住博 2013 木村一基: 実際、羽生善治は木村から1手詰みの頓死を食らったことがある(2001年竜王戦挑戦者決定三番勝負第1局)。 柳瀬尚紀: 将棋ファンであり、将棋に関する著作を米長邦雄や羽生善治との共著で数冊出している。 金田達也: 学習まんがスペシャル 羽生善治(ストーリー:三条和都、2019年) 須賀原洋行: 深浦康市と羽生善治をモチーフとした「将棋星人」のジョークは須賀原自身の投稿が初出であると主張している。 広瀬章人: 第56期(2015年度)王位戦では、羽生善治王位への挑戦権を得たが、1勝4敗で敗れた。 稲葉陽: 2年連続の名人挑戦権獲得を掛けたプレーオフでは羽生善治に敗れた。 先崎学: 第1期(1988年度)竜王戦6組で優勝(5組昇級)し、本戦トーナメントでは2回戦に進出(羽生善治に敗れる)。 石田和雄: 第2代竜王・羽生善治への挑戦権を争う本戦トーナメントでは、中原誠らを破り挑戦者決定三番勝負に進出するが、谷川浩司に0-2で敗れる。 広瀬章人: さらに挑戦者決定戦では、白組優勝の羽生善治名人を破り、タイトル初挑戦(六段昇段)。 土佐浩司: 羽生善治が七冠王だった1995年に、コンピューター将棋について「10年くらい後にコンピューターがプロ棋士を負かす時代が来る」と予想していた(「将棋年鑑1996年」)。 畠田理恵: アヒルやウサギ等の動物に関連した話題や画像のツイートが数多いが、夫の羽生善治や将棋関連の話題もツイートすることがある。 岡本信彦: 一・二・三! 羽生善治の大逆転将棋(2018年1月3日・2019年1月3日・2020年1月2日、NHK BSプレミアム) 福崎文吾: このタイトルは翌期の第40期王座戦で羽生善治に0-3で奪われ、その後羽生は王座のタイトルを19期に渡り保持し続ける事となる。 郷田真隆: 同学年の羽生善治が、すでに初の竜王位に就いていた頃のことであった。 菅井竜也: 1回戦で羽生善治名人を破ったのを皮切りに、豊島将之六段、屋敷伸之九段を下して決勝に進出。 森下卓: 1994年度では第20期棋王戦で羽生善治に挑戦したが、0勝3敗のストレートで敗退。 佐藤康光: 47、48期(1998、99年度)の羽生善治以来、同大会9年ぶり3人目の連覇を達成した。 山田敦子: 激突!東西の天才 将棋名人 羽生善治 伝説のチェス チャンピオン ガルリ・カスパロス(ナレーション・2015年3月21日) 深浦康市: 2003年(2002年度)、準タイトル戦の第21回朝日オープン将棋選手権において、初代朝日選手権者の堀口一史座に挑戦し3-1で奪取して、2代目の朝日選手権者となる(翌年、羽生善治に奪取される)。 神吉宏充: 2000年11月、将棋の日恒例の「次の一手名人戦」(羽生善治 vs 丸山忠久戦)にゲスト参加したところ、最後まで正解し続けて「次の一手名人」となった。 佐藤康光: 2008年10月、フランスのパリで行われた第21期竜王戦七番勝負第1局(渡辺明竜王対羽生善治名人)の記録係を務めていた中村太地が会場設営の際に感電する事故があり、解説で同行していた佐藤(当時棋王)は「もしものことがあれば私が記録係を務めます」と申し出ていた。 保坂和志: 将棋が趣味であり、羽生善治の将棋がいかに画期的であるかを論じた本、『羽生〜21世紀の将棋〜』も刊行している。 堀口一史座: 三段時代は自ら志願して羽生善治の対局の記録係を数多く務めた。 藤井聡太: 第43回将棋日本シリーズでは、羽生善治九段、稲葉陽八段、斎藤慎太郎八段に勝利し、初優勝を果たした。 井上慶太: 羽生善治が1996年2月14日に七冠独占を達成した6日後の2月20日、オールスター勝ち抜き戦で井上が羽生に勝ち、「羽生七冠」に初めて勝った棋士として話題となった。 森内俊之: 自身の師匠である勝浦と、羽生善治の師匠である二上達也は、いずれも渡辺東一名誉九段門下である。 |
羽生善治の情報まとめ

羽生 善治(はぶ よしはる)さんの誕生日は1970年9月27日です。埼玉出身の将棋棋士のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/27 14:59更新
|
habu yoshiharu
羽生善治と同じ誕生日9月27日生まれ、同じ埼玉出身の人
TOPニュース
羽生善治と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター